 
第2話(その2)
アルフリートは深淵の眠りから目覚めていた。体中に汗をかきシーツを濡らしていた。
「嫌な夢だった。忘れていたはずだったが」
ベッドから起き上がり、鏡に映った自分の顔を見る。そこには、やや疲れた冴えのない顔があった。
「まいったなあ、これから王宮に行って陛下に会うというのに」
言った瞬間、アルフリートは自分がこのような夢を見た理由に気が付いていた。
「レティシアに会うかもしれないな」
頭では忘れたつもりであっても、心には深い傷となって残っていた。幸いにして、彼は彼女に対して恨みなどもっていなかったが、あまり会いたくない人間には違いなかった。
アルフリートはさっぱりするためにシャワーを浴びた。戦略的な勝利ではなかったとはいえ、形上は勝利を収めての凱旋将軍である。あまりみっともない姿をアスラールの前には見せたくなかった。汗を流し髪を洗い、クリーニングから還ってきたばかりの深緑の軍服に身を包んで、彼は軍の官舎を出ることにした。
「ブー!」というブザーの音が鳴って客の到来をコンピュータが報せた。アルフリートは慌ててモニター付きのインターホンのスイッチを入れ、客の顔を覗いた。
「お早ようございます。クライン中将」
「ん?何だ、ファン・ラープ准将か。いったい何のようだ、こんな朝っぱらから。……それからだいたい私は中将じゃないぞ、まだ少将だ」
「いえ、特別の用事があったわけではないのですが……今日は早く起きましたのでサービスに起こしてさしあげようと参上いたしました。」
間の抜けたファンの顔を見せられて、アルフリートはホッと気持ちが落ち着くのを感じた。軍人として生きてきたこの五年の歳月が彼を完全に戦場の人間に染めていた。決して戦争が好きなわけではない。しかし、こうして戦場を離れても、軍での仲間に会うと何故か落ち着くのだった。
「……ありがとう、ファン」
アルフリートは戦場での彼と違って素直に礼を述べていた。
不意打ちをくらったかのような表情をしたのはファン・ラープだった。
「えっ!今なんと」
ファンがアルフリートにあいさつしに来たのは、彼をからかってやろうという低い次元の発想から生まれたものであった。戦場から帰還してまさか一人の夜は過ごしていまい。どこかの美姫がいっしょにいるにちがいない。そう想像して出向いたファンだったが、現実は思いっきり肩透かしをくらうものだった。
「別にいい、それよりも私は王宮に行かねばならないんだ。また後で会おう」
アルフリートの表情に笑みが浮かんでいた。
ファンは理解しがたげに頭をかしげていた。
現在クレティナス王国の王位に即くのは、王国史上最高の名君と噂される第一五代アスラール三世である。建国王リュシターの偉業さえもかすめさせるその勇名は、小国であったクレティナスを銀河の五分の一を支配する強国に成長させたその業績に起因する。厳密に言えば、その業績は彼が王位に即く前の王太子時代に成し遂げたものであったが。
アスラールが王国の実権を握って以来この一○年間、クレティナス王国は実に百数十回にも及ぶ戦闘を繰り返している。アスラール自ら行なった二○数回の親征もその中に含まれているのだが、驚くべきはこの間のクレティナス軍の勝率である。双方引き分けと認められる戦いを除いてのこの一○年間の勝率は、なんと九割りを越えていた。百戦して百勝というわけではなかったが、その数字は隣国を脅威に陥れるのには十分であった。
しかし、その例外として存在したのが銀河皇帝を擁する千年帝国である。
ベルブロンツァ恒星系で行なわれた千年帝国とクレティナス王国の四度目の戦闘は、実質的な意味ではクレティナス軍の勝利に終わっている。これは、直接指揮をとった相手が神将と呼ばれるユークリッド・タイラーでなかったとはいえ、クレティナス軍にとっては千年帝国軍に対する初めての勝利であった。
それゆえに、たとえそれが戦略的な勝利でなくとも、政治的に、あるいは心理的に価値のあるものであり、クレティナス軍首脳部は戦いの功労者であるアルフリート・クライン少将に対して、称賛と中将への昇進を与えることにした。信賞必罰、クレティナス軍の強さはその徹底した実力主義にある。能力のある者には身分を問わず重職が与えられ、功績のあった者には恩賞が与えられるのである。だがそれらを含めても、クレティナスは依然、王侯貴族といった階級の支配するところにあった。
特権を排除し、すべての国民に平等な機会が与えられ、階級に縛られることなく自分の生きたいように生きられる自由な社会、ジークフリード・クラインが求めた、そして、アルフリート・クラインが目指している社会は、千年以上も昔に葬り去られたそんな世界であった。
アルフリートが王宮に参内したとき、国王アスラール三世は執務を終えて王の私宅である後宮に下がっていた。通常、いかなる場合があっても国王の許しがなければ、男はそこに入ることができない。アスラールが王位に即いてから女官の数は著しく減っていたが、後宮は現在でも女の城としての地位を保っていた。
アルフリート・クラインは医者と侍従以外の平民出の男としては初めて後宮に通されることになった。アスラール三世が公的にではなく、私的な意味でアルフリートに会いたいと強く希望したからである。
王宮も同様だが後宮など王の近くの建物は、すべてきらびやかな調度でととのえられていた。アルフリートにとっては見る物すべてが目新しく、多くの人の財の蓄積によって創造された壮麗な空間にその視覚を圧倒された。
かなり年を取った黒服の侍従長に案内されて、アルフリートは後宮の一室に通されていた。そこは、見た目にはそれほど贅沢な調度品はなかったが、部屋の作りが独特の雰囲気を醸し出す、後宮にしては少し小さいほうの部屋であった。
「クライン少将、よく来てくれた。さあ、入ってくれ」
アルフリートを待っていた王の第一声は、主君と臣下というよりも友が旧友を呼ぶときのようなくだけたものであった。
「ハ、ご無礼申し上げます」
深い一礼をして部屋に入ったアルフリートは、用意されたソファーに腰を降ろすと、恐る恐る視線を上げた。そして、次の瞬間、彼の瞳には古代の神にも似た美しさを持つ国王と、その横に並ぶ優しい目をした美しい女性が映っていた。
「レティシア!」
口だけは動いたが精神力で声が出るのを押さえてアルフリートは視線を外した。
「クライン少将、そのように堅くならなくてもいい。今日は王とか臣下といった関係を忘れて友人として君と話をしたいのだ。レティシアにもそう言ってある。自由に話してほしい」
アスラール三世は機嫌よく語りかけた。彼の回りの者はともかく、彼自身は彼の妻であるレティシアがアルフリートのかつての恋人であったことを知らない。アルフリートに対する配慮が欠けていたとしても仕方のないことだった。
「どうぞ、お食べになって。わたくしが作ったものですけど」
レティシアはゆっくりとした動作で小綺麗な箱からケーキを取り出すと、アルフリートとアスラールの前にそれを並べた。
王妃になってからのレティシアは以前にも増して美しかった。昔のおてんばな娘の面影はどこにも残っていない。アスラールとの会話中レティシアは、アルフリートに対して終始笑顔を見せていた。
「幸せにやっているんだろうか、アスラール陛下なら大丈夫だと思うが」
ふとアルフリートはそんなことを考えていた。表面的にはともかく、内面的には主君であるアスラールは彼にとって恋人を奪い父の死にも関係した憎むべき敵だったのだ。自分でも意外さを感じずにはいられなかった。しかし、彼の主君は人間的に好感の持てる優しい人物だった。アルフリートは理性的にそれを理解していた。
アスラールとの会話は一時間以上に及んだ。先日のベルブロンツァ会戦のことから、アルフリートが今まで戦場で経験した出来事などを次から次へと語り、アスラールはそれに興味をもって耳を傾けていた。彼は国王と言っても性格的には武段的な側面が強く、こと話が戦略・戦術の分野に及ぶと彼自身、身を乗り出して自分の理論を熱っぽく語った。
そして、時間の経つのも忘れて語り合った後、頃合をみてアスラールが切り出した。
「余が考えていたとおり、君は知勇兼備の名将のようだ。これなら余の期待に応えてくれるだろう。……実はまだ正式に決定されたことではないのだが、余は千年帝国に対抗するため高度に自由な作戦行動を許した艦隊の創設を考えている。余と王国軍司令長官の命令以外、一切の制約を受けない一種の自由艦隊だ。人事面でも大幅な権限が与えられる。どうだろう、君にその艦隊を率いてもらいたいのだが」
アスラールの提案は大胆なものだった。作戦行動の自由が許された艦隊といえば、完全な独立軍である。従来のクレティナス艦隊とは一線を画し、前線司令官に巨大な権限が与えられる艦隊となる。アルフリートは正直言って驚いた。
「そのような大任、どうして小官のような若輩者に」
「常々考えていたのだ。ユークリッド・タイラーのような名将を有する千年帝国に勝つためにはどうしたらよいのか。相手は千年帝国だけではない。この銀河には、まだ余の知らない強国が数多く存在している。しかし、それらすべてに対処するほど余の手は広くはない。そこで余は、各地で起きた抗争を速やかに解決し、余に代わって自由に戦える艦隊が必要であると考えたのだ。すなわち自由艦隊だ。その司令官は、戦術面だけではなく戦略面でも高度な判断が要求される。クレティナス軍全体の方策から各地で展開される戦況まで把握しなくてはならない。それらをやりこなすことができるとしたら、それはまだ若い有能な人物であると余は確信している」
「陛下は、それが小官であるとおっしゃるのですか」
「そうだ。期待している」
「ですが、それでは現在、小官が指揮する四四艦隊の方はどうなるのでしょうか」
「その後任なら考えてある。確か君と同期だったはずだが、グランビル少将という男だ。彼なら君もよく知っているだろうから心配あるまい」
「……承知しました。非才な身ながら全力を尽くします」
一呼吸おいて、アルフリートは応えていた。彼に対する国王アスラールの信頼は想像以上に厚い。いずれは反旗を翻すかも知れない若い司令官に対して、国王は絶対の信用を置いていていた。あるいは、アルフリートの本心を見抜いた上で、彼に権限を与えてその能力を利用しようとしているのかも知れないが。
いずれにしても、これによって大きな権限がアルフリートに与えられることになった。二五歳の赤毛の青年は、少将から中将に昇進し、第四四艦隊の司令官から第四九艦隊の司令官に任命されたのである。しかも、新設された第四九艦隊は、従来の艦隊の二倍の戦力を有し、艦数でおよそ一○○○隻を越えるものであった。
国王との会見後、後宮を後にしたアルフリートの表情は明るかった。レティシアの姿も脳裏に焼き付いてはいたが、今は新しい任務への期待の方が彼の心を大きく占めていた。遥かなる理想を抱き、より高い次元へ飛翔しなければならないアルフリートにとって、指揮権の拡大は、夢の実現への大きな前進だったのである。
|
 |
  |
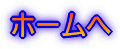
|

